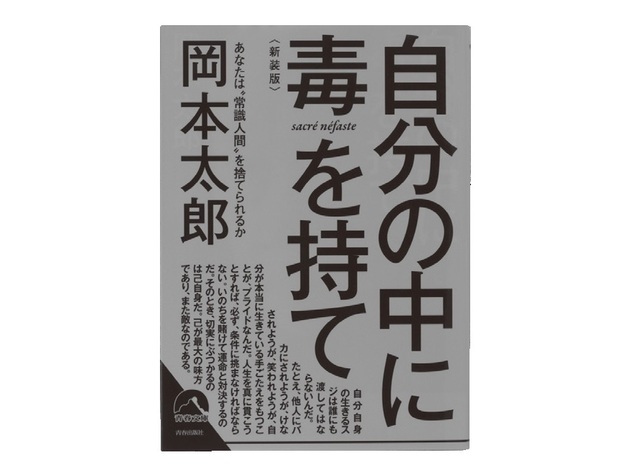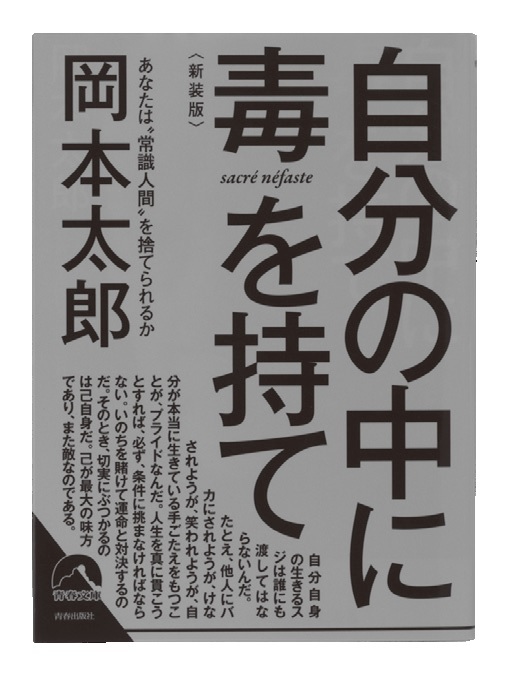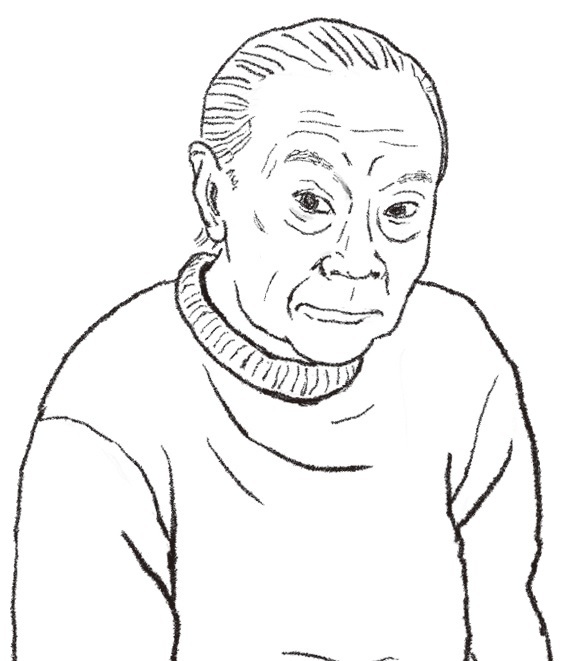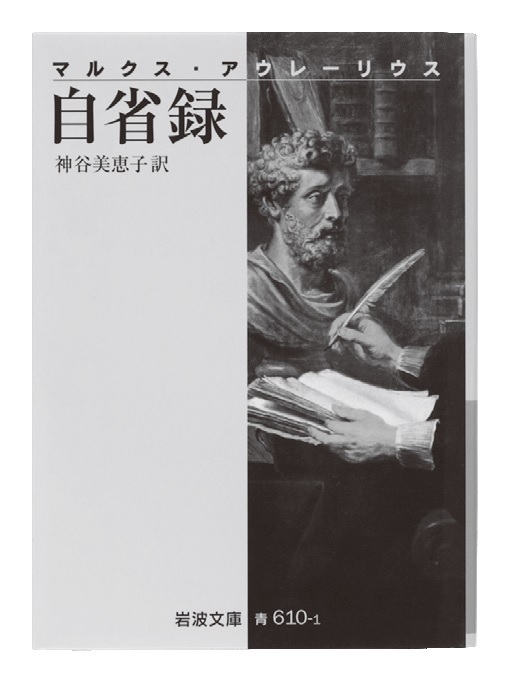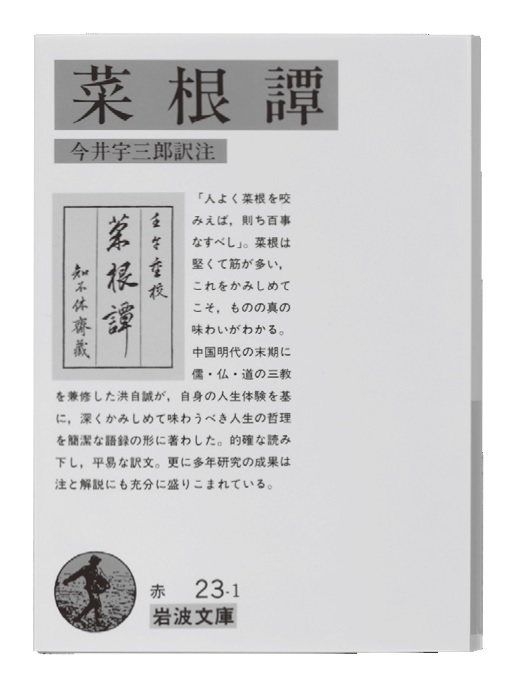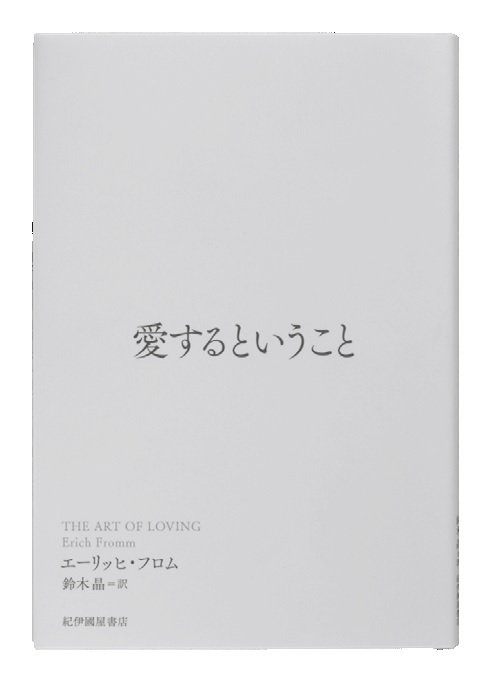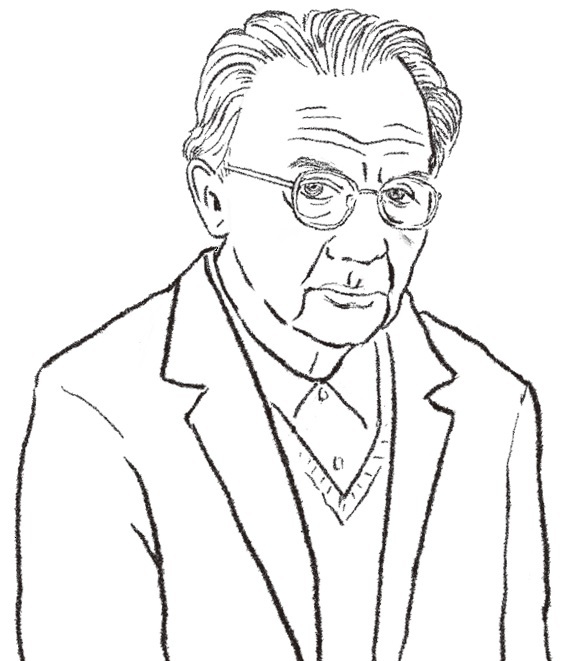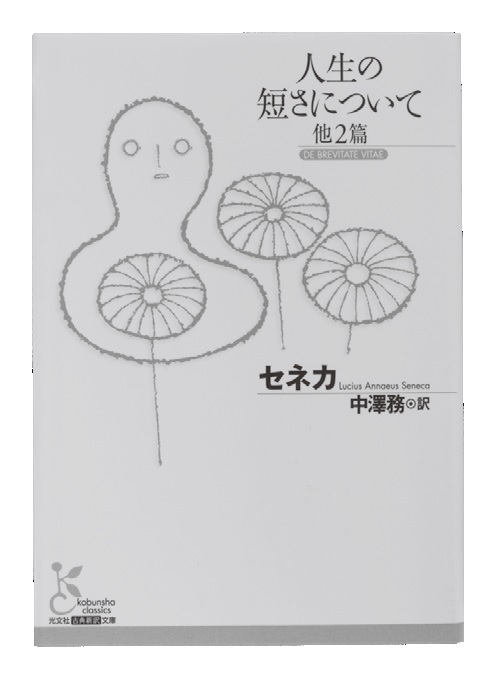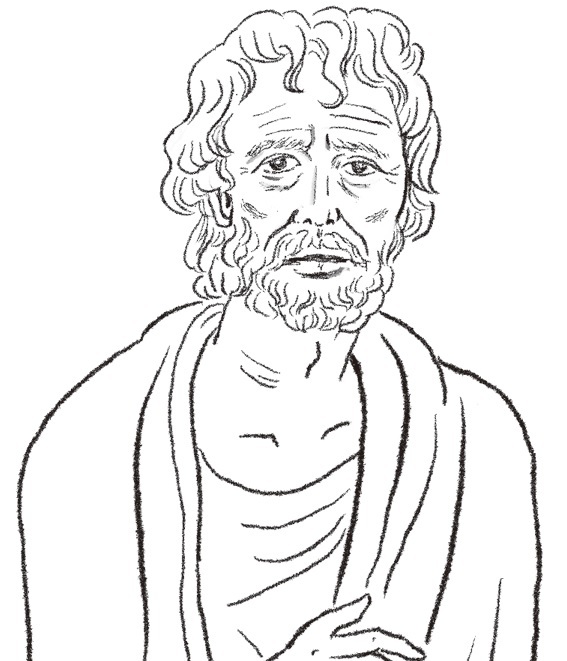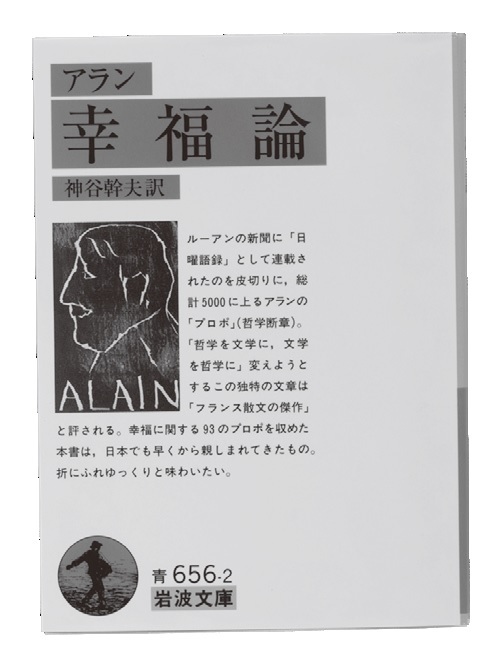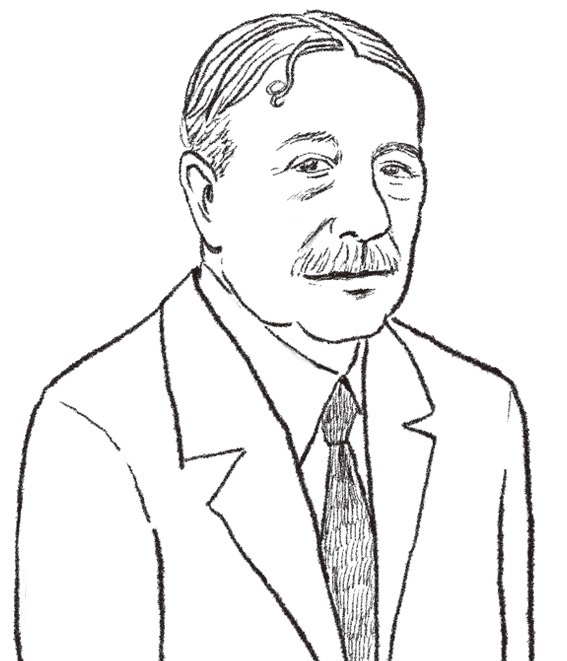今の悩みに早く答えが欲しい、もっとうまくやらなければ…。そんな焦りに支配されそうになったら。自信や自己肯定感を失わせるネガティブな気持ちを払拭するヒントを、書評YouTuberのアバタローさんが“名著”から解き明かします。
“自分を高めた”偉人たちの哲学に学ぶ。3分でわかる! 名著解説。
自信、やる気を取り戻したい時に…岡本太郎『自分の中に毒を持て〈新装版〉』
生涯芸術家による長年愛される大ロングセラー。
本書は、多くの著名人が愛読書として挙げる岡本太郎の代表的著作。箴言の宝庫だが、なかでも〈ほんとうに生きるということは、いつも自分は未熟なんだという前提のもとに平気で生きることだ〉は強烈なメッセージだ。「生きるうえでは、優れた技能やたくさんの知識を持っていなくてはいけないと一種の理想像に縛られ、それで自己肯定感を持てずにいる人がとても多いですよね。それを太郎は“型にハマっているだけ”と一蹴します。自由に明るく、その人なりのユニークさを押し出せば、未熟さも逆に生きてくる。コンプレックスも小さくなります」
青春文庫/¥814
岡本太郎(1911‐1996) 1930年代のパリで抽象芸術やシュルレアリスム運動に参画。帰国後は前衛芸術のアイコン的存在として人気を博した芸術家。哲学者バタイユとの親交も知られる。
傷つきやすさを克服したい時に…マルクス・アウレーリウス『自省録』
ローマ帝国に君臨した哲人皇帝による古典的名作。
アウレーリウスが皇帝となったのは、外敵の侵攻、パンデミック、天災など、ローマ帝国に多事多難が降りかかった時代。「自分の怒りや痛みを切々と綴ったこの手記からは、皇帝なのに人間関係で悩み、他人の目線や評価に心を乱されるさまがうかがえるんですね。彼の繊細さに共感するはず。内面を綴るうちに、彼は“感情の手前には判断がある”ことに気づく。例えば無能と言われて腹が立つなら、その中傷に自分も納得してしまったのと同じこと。コントロールできないものは最初から無視すればいいという、スルースキルも学べます」
神谷美恵子 訳/岩波文庫/¥946
マルクス・アウレーリウス(121‐180) ローマ五賢帝最後の皇帝。早くからストア哲学に傾倒し、哲人皇帝の異名も持つ。その彼が「不動心」を求めて終生綴った、自分との対話の記録が『自省録』。
人間関係で失敗した時に…洪 自誠『菜根譚』
約400年前の中国・明代の学者による処世術!
志や仕事、人生の逆境を乗り切り、幸せになるためのノウハウを、自身の人生体験を元にまとめた書。「この本の白眉は、人間関係について書かれた部分です。人との関係がギクシャクすると、自分が何か間違っていたのではないかとメンタルが削られがち。そうしたつまずきをあらかじめ排除しておくには、例えば前集一〇五にある“相手の小さな過ちをとがめず、人の隠し事を暴かず、過去の過ちをいつまでも覚えておくようなことをしなければ、自分の徳も養えるし、人の恨みを買うこともない”が有効。無駄な敵を作らない知恵に、首肯しました」
今井宇三郎 訳注/岩波文庫/¥1,067
洪 自誠(生没年未詳) 詳しい来歴は不明だが、中国・明代末期に三教(儒教、仏教、道教)を修めた著述家であろうとされている。本書は前集と後集から成り、合わせて約360の哲理を記した。
大切な人との絆を守りたい時に…エーリッヒ・フロム『愛するということ』
愛の理論と愛の技術を説く世界的ベストセラー。
愛は自然発生的な個人の体験だと思われているふしがあるが、実は修練を要する技術だというのがフロムの主張。「人を愛するためには、相手への配慮、責任、尊重、知が不可欠。かつ、成熟した人間同士に見られるものだという立場をとるので、愛することの困難さにひるむかもしれません。しかし、相手の話をよく聞こう、相手を知ろうなど、愛するための能動的な技法を具体的に教えてくれる本でもあります。また、西欧思想では否定されがちだった自己愛についても、自分を愛せない人間が他者を本当に愛することはできないと語り、肯定しています」
鈴木 晶 訳/紀伊国屋書店/¥1,430
エーリッヒ・フロム(1900‐1980) ユダヤ系ドイツ人の社会心理学者。ドイツの複数の大学で学んだ後1933年に渡米、のちに帰化。精神分析に社会的視点をもたらし、「新フロイト派」の代表的存在とされた。
せわしない日常から抜け出したい時に…セネカ「人生の短さについて」(『人生の短さについて 他2篇』に所収)
古代ローマの哲学者が語る人生の処方箋。
多くの人が人生は短いと嘆くが、「それは時間を浪費しているせいだ」と批判したのが、古代ローマの哲学者セネカ。「人は多くの時間を退屈しのぎの娯楽や無益な仕事などで無駄遣いし、まるで時間が無尽蔵な資源であるかのように生きています。それをセネカは〈多忙〉と呼び、その真逆の時間の使い方〈閑暇〉の大切さを訴えます。閑暇とは、自分が本来なすべきことをするために、自分と向き合う時間のこと。現在という瞬間も、過去の哲人たちの叡智を学ぶために使えば何かを成し遂げることができるし、そんな人生は十分に長いと語っています」
中澤 務 訳/光文社古典新訳文庫/¥990
セネカ(紀元前1‐65) ストア派と呼ばれる哲学学派の重要な人物のひとりで、政治家、劇作家でもあった。古代ローマのカリグラ帝時代には財務官として活躍。ネロ皇帝の教育係だった時期も。
生き方を見直したい時に…アラン『幸福論』
世界中で読み継がれる三大幸福論の一つ。
アランは、幸福になるのは意志の力だと考えている。「彼は、もし幸せに働きたいのであれば誰かの畑ではなく自分の畑を耕しなさい、と言います。歌を聴くのが好きなら聴くだけではなく歌ってみよう、絵を見るのが好きなら描いてみよう。つまり、幸福になるためには、傍観者を卒業しようということなんですね。人から与えられる受動的な喜びは一瞬で消えてしまうけれど、労働でも作業でも、自分で自由に取り組み、そこから学ぶのであれば、感情の一番深い部分が刺激されるし、幸福を作り出すことになる。そのための知恵が詰まった本です」
神谷幹夫 訳/岩波文庫/¥1,078
アラン(1868‐1951) フランスのリセ(高等中学校)で40年間哲学教師を務め、30年にわたり新聞に「プロポ(哲学断章)」を書き続けた。本書は5000にも及ぶプロポから、幸福に関する93を所収。