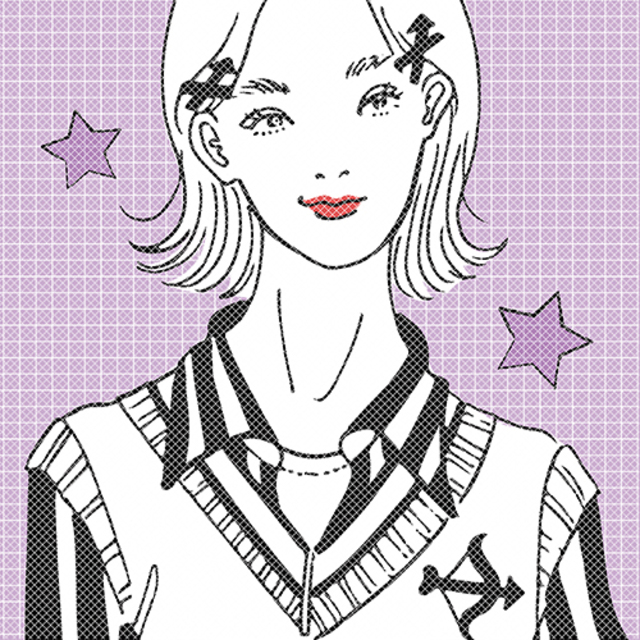今週のさそり座の運勢
illustration by ニシイズミユカ
理想像をめぐって
今週のさそり座は、過去に存在した誰かと同じ役割を果たしていこうとすること。
カール・マルクスは、1799年にナポレオン・ボナパルト(ナポレオン一世)が政府を倒した「ブリュメール18日のクーデター」と、甥のルイ・ボナパルトが1851年に議会に対するクーデターを起こして独裁体制を樹立し、翌年には「ナポレオン三世」と名乗るようになったことを対比しながら『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』を書き上げ、そこで「革命」のもつ謎について次のように説明しました。
「人間は自分自身の歴史を作るが、自分が選んだ条件の下でそれを作るわけではない。彼(※ルイ・ボナパルトのこと)はそれを手近にある、所与の、過去から与えられた条件の下で作るのである。すべての死者たちの伝統は生者の頭上の悪夢のようにのしかかる。そして、ちょうど彼が自分自身と物事を改革し、それまで存在しなかったものを創造することに没頭している、まさしく革命的な危機の時代に、彼は不安げに過去の亡霊を呼び出しては、その名前や戦闘のスローガンをそこから借り受け、昔ながらの服装をまとい昔の言葉を使いながら、その新たな世界史の場面を演じているのである。」
注意深く読めば、読者はここでマルクスがルイ・ボナパルトを単なるバカと冷笑的に論じている訳ではなく、ある種の愛情さえ込めて取り扱っていることに気づくのではないでしょうか。あなたもまた、自分が何を演じているのかということ改めて思い知っていくことになるかも知れません。
今週のいて座の運勢
illustration by ニシイズミユカ
闇に投げ込まれる
今週のいて座は、「闇の深さ」を取り戻していこうとするような星回り。
「金亀子」と書いて「こがねむし(黄金虫)」と読む。「金亀子擲(なげう)つ闇の深さかな」(高浜虚子)は明治の終わりに詠まれた句ですが、その頃の日本家屋にはまだ網戸がなく、夕方になると灯りを慕ってさまざまな虫が飛び込んできたのだそうです。中でも黄金虫は手ごろな大きさで、捕まえるとどこかへ投げたくもなるもの。作者もふと手に取って、戸外に放り投げたのでしょう。すると、キラッと光ってすぐに闇のなかに吞み込まれていった。
黄金虫の光から、闇の深さへ一気に転換していくことで、闇がいっそう濃く深いものに感じられてくるはず。「光を飲みこむ闇」とは、はるか昔より人間世界を取り囲む未知の自然に投影されてきた伝統的なイメージですが、近代化していたるところに電気の灯りが届くようになって以降の社会では次第にその本来の威厳が失われつつあるものと言えます。
そして、自然への畏敬の念を抱く機会をすっかり失ったことで、気候変動などより深刻な危機をみずから招いてしまっている現代人は、いつしか黄金虫を戸外に投げる側から、闇に投げ込まれている黄金虫の側へと立場を移してしまったのではないでしょうか。あなたもまた、そうした畏敬の念を感じさせてくれるものとしかと向きあっていくべし。
今週のやぎ座の運勢
illustration by ニシイズミユカ
些細な記憶をめぐって
今週のやぎ座は、もはや失われてしまった過去を経由してはじめて現在と遭遇していくような星回り。
新しくてどこか懐かしい――。「発見」というのはいつだって、私たちにそんな感触を伴って与えられる。例えば、岸本佐知子は父の郷里「丹波篠山」の名を冠したエッセイの中で、「いがぐり頭の十歳くらいの男の子が外から走って帰ってきて、井戸端に直行」し、たらいの中で冷やしてあるキュウリを「一本つかんでポリポリうまそうにかじ」っており、外では蝉が鳴いているという記憶を、このところ頻繁に思い出すのだと書いている。
だが、その子どもとはおそらく自分の父であり、だからどう考えても理屈に合わない。そして、ときどき自分と妹をまちがえ、自分の名前さえ忘れてしまう現在の父に丹波の写真を見せても、ただ不思議そうに眺めるだけだという。父が子供の頃、井戸水で冷やしたキュウリが好きだったのか、確かめる機会を著者は永遠に失ってしまったのだ。それを受けて、彼女は次のように書いている。
「この世に生きたすべての人の、言語化も記録もされない、本人すら忘れてしまっているような些細な記憶。そういうものが、その人の退場とともに失われてしまうということが、私には苦しくて仕方がない。どこかの誰かがさっき食べたフライドポテトが美味しかったことも、道端で見た花をきれいだと思ったことも、ぜんぶ宇宙のどこかに保存されていてほしい」。あなたも、記憶の中にある光景が今まさに失われつつあることを遠く想像してみるといいでしょう。