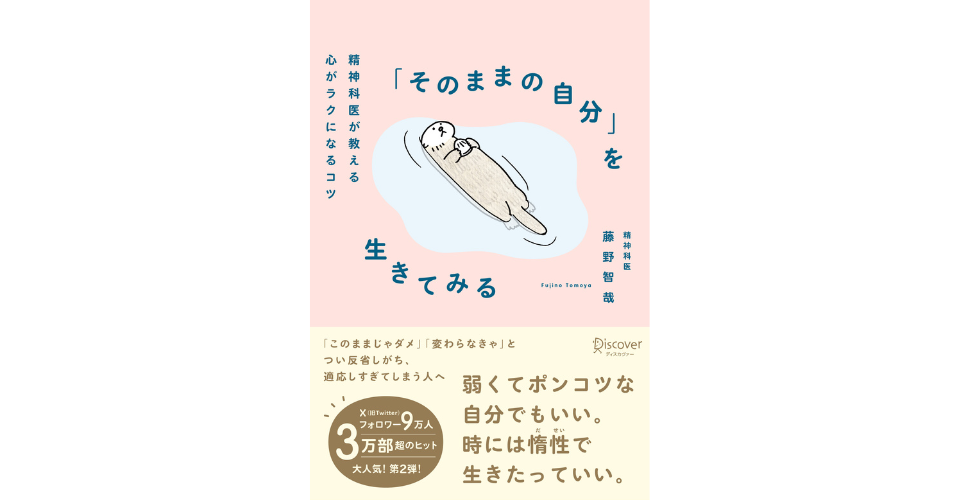春からの新生活がしっくりこないことがあるのは、大人も子どもも同じです。子どもが「学校に行きたくない」といったとき、親はどのように対応したらいいのでしょうか? メディアやSNSでゆるゆるとしたメッセージを発信している人気精神科医の藤野智哉先生に教えていただきます。
教えてくれたのは……藤野智哉先生
精神科医。産業医。公認心理師。
幼少期に罹患した川崎病が原因で、心臓に冠動脈瘤という障害が残り、現在も治療を続ける。学生時代から激しい運動を制限されるなどの葛藤と闘うなかで、医者の道を志す。現在は精神神経科勤務のかたわら、医療刑務所の医師としても勤務。障害とともに生きることで学んできた考え方と、精神科医としての知見をメディアやSNSで発信中。
著者:藤野智哉
価格:1,760円(税込)
発行所:ディスカヴァー・トゥエンティワン
理由を問いただしても、子どもが話すとはかぎらない
進学やクラス替えなど、春から子どもの置かれる環境に変化が起きたという方もいるかもしれませんね。新しい環境がしっくりこなかったり、心が不安定になったりするのは大人も子どもも同じこと。そうわかっていても、子どもから「学校に行きたくない」といわれると、親は対処に迷い、心がざわついてしまうものですよね。
藤野先生 「不登校というのは病名ではなく、何らかの理由によって子どもが『学校に行きたくない』と感じている状態のことです。学校に行きたくない理由がわかれば比較的対処しやすいですが、本人が言葉にできない場合もあり、なかなか理由を話さないこともあると思います。なんでも親と一緒だった子どもも成長とともに独立した“人”になってくるので、無理に理由を問いただしても、容易に話してくれなくなっていきます。裏を返せば、子どもが学校に行きたくないと言ったとき、その責任が親だけにあるわけではないと考えることも、大事になってきたりします」
親ができることとは
そんなとき親ができるのは、「子どもが頼りやすい空気をつくっておくこと」と藤野先生。あわてて何かをしようと思わずに、まわりを頼ってもいいと子どもに伝えていくことが、とても大事なのだそうです。
藤野先生 「大人もそうですが、子どもって『助けて』というのがすごくカッコ悪いことだと思っている場合が多いんです。ほとんどの子どもは、親がつらくて泣いている姿を見たことがないから、大人は完璧で、それに比べて自分はなんてカッコ悪いんだろうと思ってしまうわけです。でも、大人だってしんどくなることはありますよね。だから、親もしんどいと感じることがあり、助けを求めるのはカッコ悪いことではないと伝えるのはとても大事です」
藤野先生 「もうひとつめちゃくちゃ大事なのが、いざというときは親が助けてくれるという信頼感を子どもにもってもらうことです。たとえば、『お父さんとお母さんが困っていたら、あなたは助けたいって思う?』と子どもに聞いてみてください。子どもはきっと、助けてあげたいと思うと答えるでしょう。そうしたら、『お父さんとお母さんも同じように、あなたを助けてあげたいと思っているんだよ』と伝えてみてください。こうした思いは、できるだけ日常的に伝えておけるといいですね」
家で過ごすルールを親子で話し合おう
藤野先生 「親はどうしても、子どもにはほかの子と同じであってほしいとつい望んでしまうものです。そう感じるのは仕方がないことではありますが、ほかの子と同じであってほしいと子どもに押しつけるのは、できるだけ避けてほしいです」
藤野先生 「とはいえ、学校に行かないのであれば、そのあいだ家でどんなふうに過ごすのかというルールづくりは、早い段階にしたほうがいいと思います。常時ゲームなどやりたいことが好きなだけできるような環境にしていると、抜け出しにくくなることがあるからです。ゆくゆくは、子どものゴールはどこにあるのか、この先どうなっていきたいのかを親子で話し合って、すり合わせられるといいですね」
子どもには助けを求めてもいいと日頃から伝え、家で過ごす場合のルールやその先のことについて、親子で話し合うことが大切なのですね。親としては悩む問題ですが、藤野先生のアドバイスをぜひ参考にしてみてください。