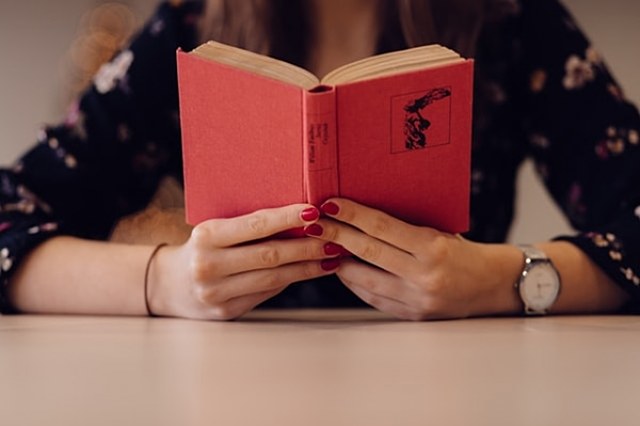(2)言葉を翻訳できていない
「察して」が顕著な例ですが、言葉足らずな人は自分の感情や考えていることを適切に言葉に置き換えて発信することが苦手です。
これは、「自分がどう思っていて、どうしたいのか。そして、どうしてほしいのか?」を、その場に適切かつ相手が不快にならないかたちで伝えるための「言葉の型」を知らないといえます。
説明がうまい人は、「適切な言い換え=自分の理解の翻訳作業」が非常に優れています。
(3)「自分=標準」と思っている
自分が分かっていることは、当然相手も分かっていると無意識的、または意識的に考えています。そのため、前提情報の共有が漏れていたり、自分の理解度に相手を合わせ説明を省いてしまったりして、結果として言葉足らずな状況を生み出してしまいます。
相手と自分が、同じ言葉を同じ意味で使っているか? どの程度の理解を前提としているか? などの「気にし過ぎる」くらいの確認は、コミュニケーションにおいて重要になります。
言葉足らずの改善法
仕事でもプライベートでもさまざまな問題が生じる「言葉足らず」。改善する方法は以下の3つです。
(1)頭の中で整理してから話す
思い付いたことをそのまま口にしたり、考えながら話したりすると、結局何が伝えたいのか分からない会話になりやすいです。
人は、会話の流れを推測しながら話を聞いています。言葉足らずな人は、その推測を悪い意味で裏切ります。「分かっているだろう」と主語を省いたり、考えながら話したりするために、自分の頭の中で出た言葉をさも話したかのように自然に飛ばし、聞き手を困惑させるのです。
思ったことや言いたいことは、整理してから話し始めるようにしましょう。すぐに回答を求められ焦る場合は、「ちょっと考えを整理します」という一言を伝えれば問題ありません。
(2)絶対に伝えることを決めておく
言葉足らずの人は、ストレートな物言いが苦手で、回りくどい言い方をしてしまう傾向があります。「察して」に限らず、周りの空気を読んで意見を合わせようとしてしまうと、奥歯にものが挟まった表現になってしまうのです。
「今日の話の中で絶対に伝えること」を整理した上で、結論から話し始めましょう。回りくどい言い方から相違が生まれてしまうことを忘れないでください。
(3)主語を意識して話す
主語を付けずに話すのが癖になっている場合があります。これは意識的に「主語から話そう」とするだけで改善します。脳内で補足しないで、全部話すことを意識しましょう。
本人は自分で話しているため、誰の何を話しているか理解できていますが、聞き手からすると「今何の話だ?」と話の全体像がつかめなくなってしまいます。「誰が」「何が」という主語をきちんと話すことをまずは心掛けてください。
正しく自分の思いを伝えよう
人と人とのコミュニケーションの基本は言葉です。もちろん補う別の要素はあれど、「言葉」が、自分の意図しているものとして伝わるかどうかは非常に重要です。
また、言葉足らずも含めた「適切な言葉のチョイス」「伝え方」は、意識して訓練することで改善できます。「話し下手だから」「自分は営業的なコミュニケーションが苦手だから」と逃げてしまわず、「言いたいことは何か? それを適切に伝える言葉は何か?」を意識しましょう。