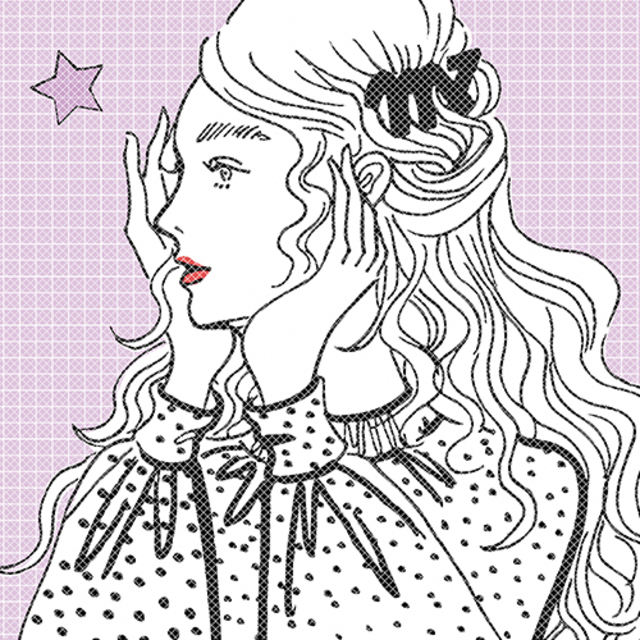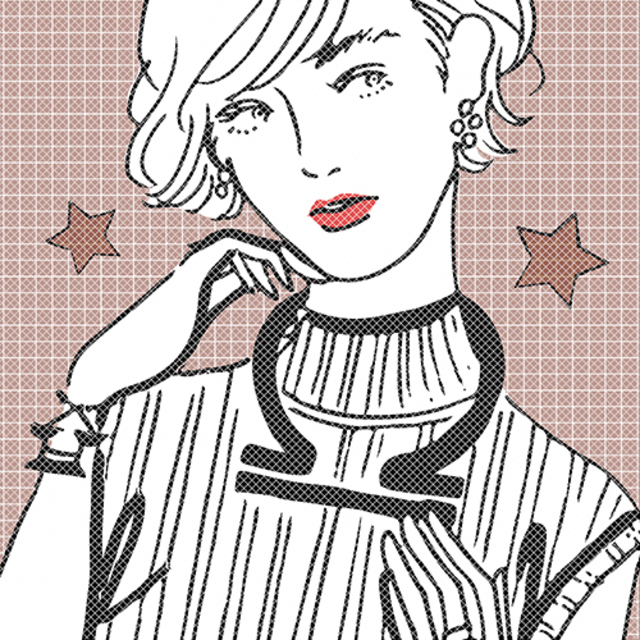今週のかに座の運勢
illustration by ニシイズミユカ
場所的個ということ
今週のかに座は、対する相手も、自分自身も、どちらも特別扱いしないようフラットに徹していくような星回り。
“ぜひ治そう”という気持ちはかえって視野狭窄を起こす、ということは精神科医やカウンセラーに限らず、かつては結核医にもよくあったそうです。それは大抵の場合、相手がやりがいのある患者で、時間をかけても惜しくないと思わせる魅力があり、治療する側が「自分が破滅しても患者が救われればいい」という思いに駆られてしまう。
精神医学者の中井久夫は、そうした投影に陥らないためには、医者なら「医者」、臨床心理士なら「臨床心理士」というように、役割的な自己規定を以って対するのが一番よく、そこから外れれば外れるほど、患者の幻想的な側面を肥大させ、治療を困難にしていくことになるのだと述べていました。
そして、できるだけ「しらふ」的な雰囲気を保って、生活の資を稼ぐための仕事としてやっているのだという裏表のない「しらふ」的な態度に徹して、場合によっては、波長を外すとか、とぼけるなどして、「甲斐なき努力の美しさ」みたいな誘惑的な道に入り込まないよう十分に注意しなければならないのだと。あなたもまた、さめたニュートラルさや距離感を大切にしていくべし。
今週のしし座の運勢
illustration by ニシイズミユカ
ひびき
今週のしし座は、深い寂寥を伴っていくような星回り。
「湯豆腐やいのちのはてのうすあかり」(久保田万太郎)で見つめられているのは、たぎってきた湯豆腐が灯にゆれる光。それは、作者のこころのなかで、みずからの命そのものの光と一体となっていたのでしょう。
当時作者は劇作家として華々しい成功を収めており、文化勲章も受賞していましたが、私生活ではさまざまな困難に遭遇しており、妻の自殺、長男の病死、それに再婚した妻とも不和となっていました。そんな中、おそらく作者の心を癒してくれたのは、再会後まもなく一緒に棲み始めた昔なじみの女性の存在だったのですが、精神的支柱だったその女性も脳溢血で急逝してしまいます。
掲句が作られたのは、その10日後ほどのことであり、「うすあかり」という結びに何かしら救いを求める心理や祈りのようなものが感じられるとしたら、それは作者の深い悲しみとも寂寥とも定かならぬ実感ゆえでしょう。そして作者もまた、同じ年のうちに赤貝をのどにつまらせて急逝しています。あなたもまた、願わくば作者のようにできるだけさらりと胸中を開示していきたいところ。
今週のおとめ座の運勢
illustration by ニシイズミユカ
ウッホ、ウッホッホ
今週のおとめ座は、予期せぬ出来事を受け入れていこうとするような星回り。
それはまるで、安部公房の『砂の女』の主人公のごとし。アマチュア昆虫採集家の仁木順平は、新種の昆虫を探しに海岸沿いの砂地へ出かけ、たえず形を変える砂丘によって外界から隔離された村に行き着く。そこには地表から15メートル掘り下げた穴の底の住居に住む人々がおり、彼らは家が埋もれてしまわないよう、毎日夜になるとバケツ何杯分もの砂を掻き出し、地上にいる村人にロープで引き上げてもらっていたのでした。
順平はそんな穴のひとつに誘いこまれ、その底にあった若い未亡人の家で、砂を掻き出す作業を手伝うことに。しかし、思いがけないことに、翌朝目を覚ますと、穴の外へ出るためのはしごが外されてしまっていたのです。それ以来、順平はなんとか外へ逃げ出そうと試みるものの、砂を運搬道具に入れ、地上の村人に引き上げてもらう作業を続け、合間に食事をしたり眠ったりするうちに、次第に新しい奇妙な生活を受け入れ始めている自分に気付きます。
あなたもまた、砂の壁に包囲されてしまった主人公のように、急な人生の変転があったとしても、そう悪くないものだと思い直してみるといいでしょう。
今週のてんびん座の運勢
illustration by ニシイズミユカ
透明な不在
今週のてんびん座は、ただただ感性的な吐息を漏らしていくような星回り。
沈黙が続くなか、言葉を発したものがあった。しかし、言葉を口にしたものは、人間ではなく、飼っている鳥であった。窓の外は見渡す限り、冬らしくひっそりとしていて、いつも以上に寂れているように感じられた。
「冬ざれやものを言ひしは籠の鳥」(高橋淡路女)は、人恋しさを確かめている句でしょう。「鳴きし」ではなく、あえて「言ひし」としているところからも、誰かと言葉を、それもできるだけ何気ない、ごく自然な会話を交わしたいという気持ちが溢れてかえっています。
作者は結婚の翌年に早くも夫と死に別れており、掲句においても、その夫の不在を改めて確かめているところがあったように思います。しかしそうした渇望こそが、飯田蛇笏が女流界一とも評した大正期を代表する俳人としての活動の原動力ともなっていったのではないでしょうか。あなたも、そうした言葉への渇望を痛感していくことになるかもしれません。